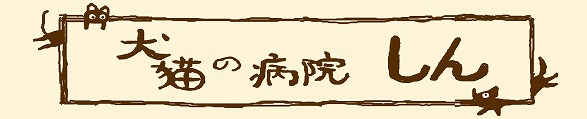
  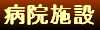 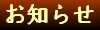 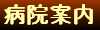 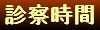
 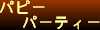  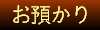  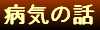
~生活の話②~
知っていて欲しい事
こんな事やあんな事
なにがこの子にとってベストなのか
一度くらい真剣に考えてもらえれば幸いです。
犬との生活について思う事
~これから犬を飼おうと考えている方へ~
人間社会に暮らす犬が「ペット」ではなく「パートナー」「コンパニオン」と呼ばれるようになってずいぶん経ちます。
実際には、いまだにペットとすら言えない環境で飼育されている犬たちもいますけれども。
私自身は、愛犬との生活はパートナーとの暮らしと言うよりも育児に近いものと思っています。
ごはんの用意をして、排泄の始末をし、一緒に遊び、健康に気を使う。
その生活の中で、もっと喜ばせたい、より快適に過ごさせてやりたいと試行錯誤し、
他人に迷惑かけないように憂うのが親心。
その過程の中で「やっぱりうちの子が一番かわいい」と誰もが立派な親バカになっていくはずです。
人間の子育てと愛犬生活の大きな違いがふたつ。
一つ目は、犬たちは親離れしないという事。
二つ目は、どんなに頑張っても、親である飼い主よりも先に天寿を全うしてしまうという事。
この2点から、これから犬を飼おうかという相談を受けた時に確認していただいている事があります。
「育児をする覚悟」
「介護をする覚悟」
という点です。
病気になるかどうかは別問題として、
ほとんどの事故(誤飲・怪我・逸走など)は親が目を離したときに起きています。
これはその子が悪いのではなく、そういう環境でそういう状況にした親が悪いのです。
そうならないためには24時間一緒にいる必要があります。
目を離すのであれば、危険を排除した環境を作らなければいけません。
家内での話は、各家庭で方針があるでしょうが、
少なくとも公共の場では、それなりのルールを守らなければなりません。
排泄などで汚してしまったら親が片づける、
物を壊してしまったり、誰かを傷つけてしまったら、
親が責任を取るというのは誰でもわかるマナーだと思うのですが、
実際、親として責任を果たせていないのに公共の場を利用している方もいるようです。
公園内とはいえ、ノーリードで歩かせているというのは論外でしょう。
育児する覚悟というのは餌を与えて成長させるだけではなく、
社会に対して、その子の責任まで面倒みるという事です。
ある程度年齢を重ねてくれば老いというものには抗えません。
今まで出来ていたことが出来なくなったり、
その世話で時間も労力もかかってしまったりします。
立てなくなった大型犬では毎回の排泄でも苦労します。
夜泣きや転倒などによる騒音は近所に迷惑をかけてしまうかもしれません。
認知症(痴呆)のような症状の子での介護では、ろくに睡眠時間が確保できなくなったりもします。
あるいは突然の病気で看護が必要になるかもしれません。
病気にもよりますが、治療費用や通院時間・看護の労力といった負担がかかります。
これが、10年後かもしれないし、15年後かもしれませんが、わが子に訪れるかもしれないのです。
その時に、介護するだけの覚悟と余裕があるといいのですが。
「今までありがとう」と感謝していく時間でもあるのですが、心にその余裕が持てなければ
サヨナラの時間が寂しいだけの悲しいものになってしまいます。
犬と暮らすという事は、家族がふえるという事。
とても素敵で楽しいことです。
助けてくれたり、慰めてくれたり、励ましてくれたり。
そういうものをもらうだけじゃなくて、こちらも時間と手間をかけていく必要もあります。
愛情なく犬を飼うだけであれば、それは「めんどくさいお世話」の連続でしかありません。
最期を迎えるときに、「この子がいてよかった」と思えるようにしたいのと同時に、
その子が「人間と暮らせてよかった」「この家族でよかった」と思えるような人生であって欲しいなと思います。
|